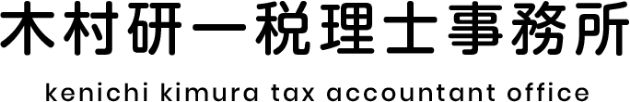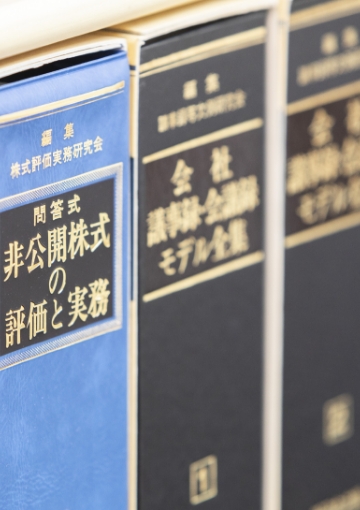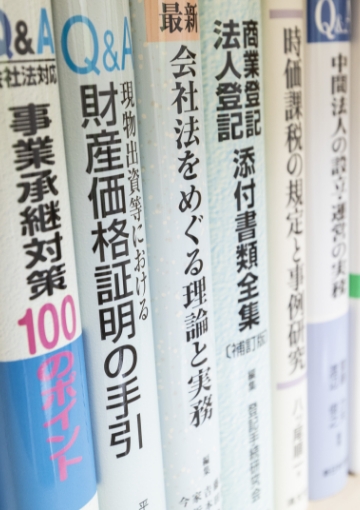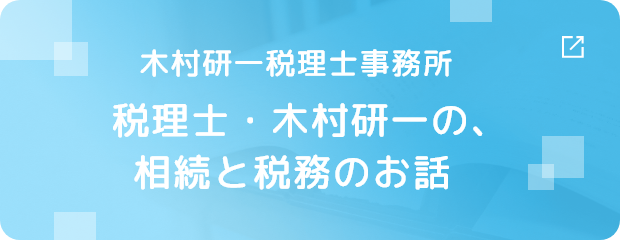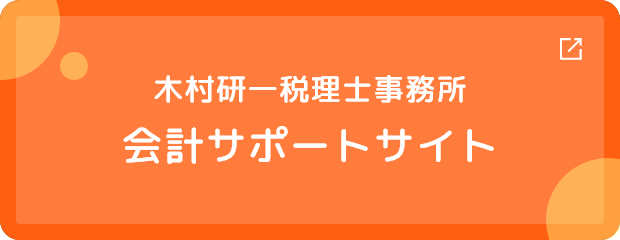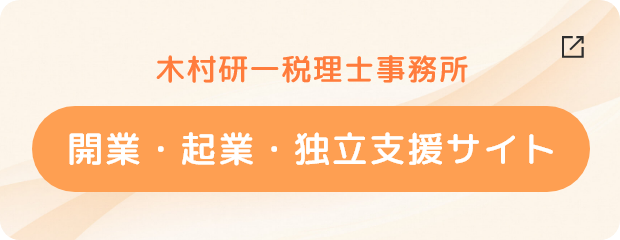こんなことで
お悩みではありませんか?
- インボイス登録が本当に必要なのか判断がつかない
- 下請けの立場で、取引先から登録を求められている
- 免税事業者のままでいたいが、取引を切られないか不安
- 登録したら消費税の納税額がどれくらいになるか心配
- 請求書のフォーマットをどう変更すれば良いかわからない
- インボイス未登録の取引先への対応に困っている
- 経過措置が終わった後のことが不安
- 経理システムの見直しが必要だがどうすれば良いかわからない
このようなことでお悩みでしたら、お気軽に京都市右京区の木村研一税理士事務所へご連絡ください。
インボイス制度への対応をサポート
インボイス制度とは?

2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)。正式な請求書を発行できる事業者として登録するかどうか、多くの事業者の方が悩まれています。
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除に関する新しいルールです。登録事業者から発行された適格請求書がないと、取引先は消費税の控除を受けられなくなります。
京都市右京区の木村研一税理士事務所では、制度開始前から多くのご相談に対応してきました。お客様の業種や取引先の状況を詳しくおうかがいし、登録の必要性を一緒に考えます。
登録が必要かどうかの判断基準
インボイス登録の必要性は、お客様の事業内容によって異なります。
登録を検討すべきケース
- 取引先が主に事業者(B to B)の場合
- 大手企業との取引がある場合
- 今後も事業拡大を考えている場合
登録を急がなくても良いケース
- 売上先が一般消費者中心の場合
- 1万円未満の少額取引が中心の場合
- 免税事業者のメリットを活かしたい場合
当事務所では、お客様の売上構成を詳しく分析し、登録によるメリット・デメリットを具体的な数字でご説明いたします。
経過措置の重要性
現在は経過措置期間中で、インボイス登録をしていない事業者からの仕入れでも80%は控除可能です。しかし、この割合は段階的に減少していきます。
経過措置のスケジュール
| 2023年10月~2026年9月 | 80%控除可能 |
|---|---|
| 2026年10月~2029年9月 | 50%控除可能 |
| 2029年10月以降 | 控除不可 |
特に2026年10月に50%になるタイミングで、取引先から登録を求められる可能性が高まります。今は様子見でも、3年後を見据えた準備が必要です。
下請け事業者の方へ
「取引を切られたら困る」という不安から、インボイス登録を迷われる下請け事業者の方が多くいらっしゃいます。
しかし、すべてのケースで登録が必要なわけではありません。下請法の保護もあり、インボイス未登録を理由とした一方的な取引停止は認められていません。
当事務所では、お客様の立場に立って、取引先との関係性も含めた総合的なアドバイスを行います。
支払う側の事業者の方へ
インボイス未登録の取引先への支払いで、消費税を二重に負担することになってお困りの事業者の方も多いのではないでしょうか?
経過措置があるとはいえ、20%分(将来的には50%、100%)は控除できません。かといって、長年の取引先に登録を強要することも難しい状況です。
当事務所では、取引先との関係を維持しながら、税負担を最小限に抑える方法をアドバイスいたします。
実務的なサポート内容
インボイス制度への対応は、登録申請だけでは終わりません。実務面での様々な変更が必要です。
登録前のサポート
- 登録の必要性判断
- 登録タイミングのアドバイス
- 適格請求書発行事業者の登録申請代行
登録後のサポート
- 請求書フォーマットの変更支援
- 登録番号の管理方法指導
- 経理システムの見直し提案
- 取引先への通知文書作成
20年以上の実績を持つ当事務所が、煩雑な手続きをわかりやすくサポートいたします。
まずは無料相談から

インボイス制度への対応でお悩みの方は、まずは無料相談をご利用ください。
お客様の業種、売上規模、取引先の状況などを詳しくおうかがいし、登録の必要性から実務対応まで、トータルでサポートいたします。
制度は今後も変更される可能性があります。当事務所では常に新しい情報をキャッチし、お客様に適切なタイミングでお伝えして参ります。
法人・企業のお客さまのサポート