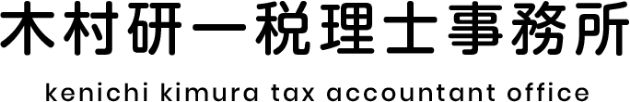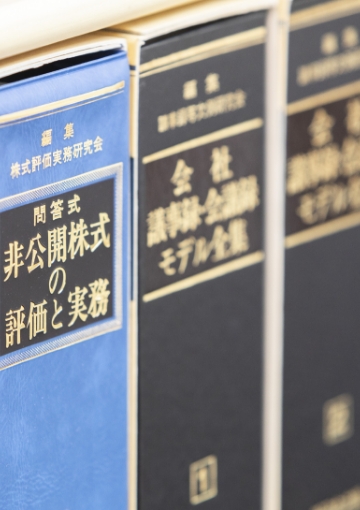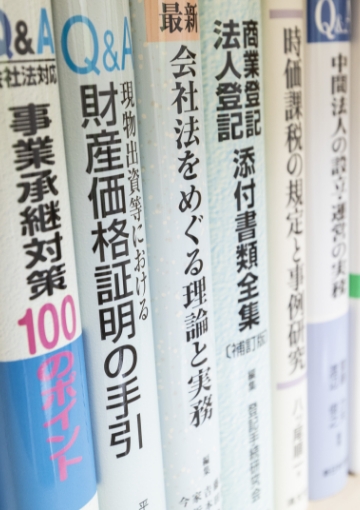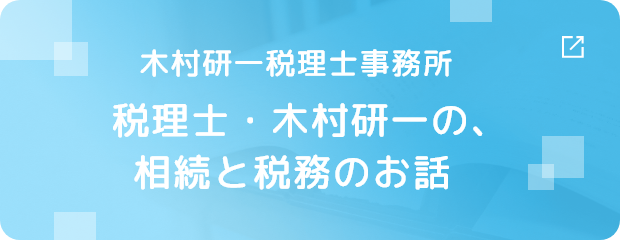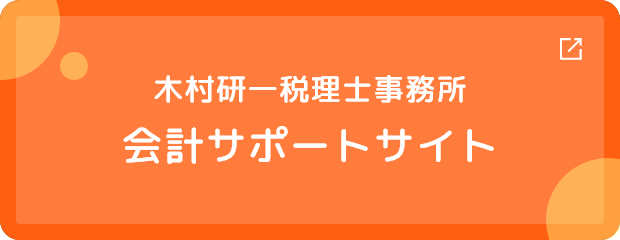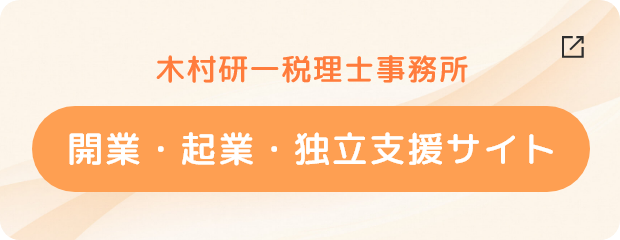フリーランスの税金を体系的に理解する
フリーランスが納める4つの税金
フリーランスとして働き始めると、会社員時代とは異なる税金を自分で納める必要があります。主な税金は4種類です。
所得税
所得税は、1年間の所得に対してかかる国税です。所得が増えるほど税率が上がる累進課税で、5%から45%まで7段階に分かれています。
住民税
住民税は、前年の所得に基づいて計算される地方税です。税率は一律10%(都道府県民税4%、市町村民税6%)ですが、前年の所得にかかるため、独立1年目は負担が軽く、2年目から本格的な納税が始まります。
個人事業税
個人事業税は、所得が290万円を超えた場合にかかる都道府県税です。税率は業種により3%から5%で、ほとんどの業種は5%です。
消費税
消費税は、売上が1,000万円を超えると課税事業者となります。インボイス制度により、売上1,000万円以下でも登録すれば課税事業者となる場合があります。
京都市右京区の木村研一税理士事務所では、これらの税金を総合的に管理し、年間の納税スケジュールをサポートいたします。
所得税の仕組みと節税対策

所得税は「売上-経費-控除=課税所得」に税率をかけて計算します。つまり、経費と控除を適切に活用することが節税の基本です。
経費については、収益を得るために必要な支出が計上できます。自宅で仕事をする場合の家賃や光熱費も、仕事で使用した割合を家事按分として経費にできます。ただし、グレーゾーンもあるため、適切な判断が必要です。
青色申告を選択すれば、最大65万円の特別控除が受けられます。さらに、赤字を3年間繰り越せるメリットもあります。白色申告と比べて記帳の手間は増えますが、節税効果は大きくなります。
当事務所では、見落としがちな経費のアドバイスや、青色申告の導入支援を行っています。
予定納税という落とし穴
前年の所得税が15万円以上だった場合、「予定納税」の通知が届きます。これは、今年も同程度の所得があると仮定して、税金を前払いする制度です。
7月と11月に前年の所得税の3分の1ずつを納付します。売上が減少した年は、予定納税の減額申請も可能ですが、手続きには期限があります。
住民税も含めると、独立2年目は税金の支払いが集中します。資金繰りを考慮した計画的な準備が必要です。
源泉徴収との関係
取引先によっては、報酬から源泉徴収される場合があります。原稿料やデザイン料など、特定の業種では10.21%が天引きされます。
源泉徴収された税金は、確定申告で精算されます。年間の所得税額が源泉徴収額より少なければ還付を受けられ、多ければ追加納付となります。
源泉徴収票の管理や、支払調書との照合など、意外と手間がかかる作業です。当事務所では、これらの書類整理もサポートいたします。
インボイス制度と消費税
2023年10月から始まったインボイス制度により、売上1,000万円以下でも消費税の課税事業者になるケースが増えています。
取引先が事業者中心の場合、インボイス登録を求められることがあります。しかし、登録すると消費税の納税義務が発生するため、慎重な判断が必要です。
現在は経過措置期間で、未登録でも80%は控除可能ですが、2026年10月以降は50%に減少します。この時期に再び登録の検討が必要になるかもしれません。
20年以上の経験を持つ当事務所が、お客様の業種や取引先の状況を詳しくおうかがいし、最適な選択をサポートいたします。
税金の不安を解消するために

フリーランスの税金は複雑で、一人で管理するのは大変です。「何から手をつけて良いかわからない」「正しく申告できているか不安」という声をよくおうかがいします。
当事務所では、初回相談を無料で承っています。専門用語を使わず、わかりやすい言葉で税金の仕組みをご説明いたします。
代表税理士が直接対応し、お客様の状況に応じた節税アドバイスをさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。
フリーランス・個人事業主